リアルワールドデータを用いた研究を実施するには、医学知識が必要です。
サポートする立場(疫学・統計・データハンドリング)であっても、ある程度求められます。
医療従事者の方にとって当たり前のことであっても、医学に関する基礎知識がないと話についていけません。
また、生物統計家の方で数理統計畑出身の方で医学の知識に自信がない方もおられると思います。
その他にも、英語がお得意で医療系の翻訳を目指している方にも参考になるかもしれません。
今回は、私が博士後期課程入学前に行った医学知識の勉強方法について書きます。
基礎医学について
まず、医学は、大きく分けると基礎医学と臨床医学に分けられます。
基礎医学は、解剖学、生理学、生化学、組織学、免疫学、薬理学、微生物学等からなります。
主に、人体の体のしくみについて学ぶ学問群であり、臨床医学の基礎になっています。
臨床医学に関しては、ご自分の研究分野のみ深く学ぶことで対応できます。
医師でない限り、基礎医学の基本的な知識があれば十分応用が利きます。
高校生物と細胞生物学、または分子細胞生物学
高校で生物を選択していない方は、まずはじめに高校生物を学習する必要があります。
(私は生物は既習だったため、この段階は省略しています)
高校生物を簡単に学んだ後は、細胞生物学に取り組みます。
細胞生物学は、大学レベルの学問です。
唐突ですが皆さん、人間の体は細胞からできていることは知っていると思いますが、細胞といっても色々ありますよね。
たとえば、脳細胞とか幹細胞とか、毛根の細胞とか。。それぞれ違う細胞ですが、なぜ都合よくそのように構成されるのでしょうか。
勘が良い方はお気付きかもしれませんが、実は、細胞同士は通信しているのです。(シグナル伝達といいます)
また、癌という病気はなぜ起きるのか知っていますか?(どのような病気ですか?)。
紫外線を浴びすぎると皮膚がんになりやすいそうですが、それはなぜですか?
大学レベルの細胞生物学を学べば、そのあたりの謎がとけて、これまで述べた質問に対して科学的に理由を述べることができます。
また、臨床研究ではiPS細胞培養や移植等のプロトコルも多いと思うので、それらを扱った試験の理解度が高まります。
細胞生物学は、基礎医学を学ぶうえでのベースになります。
おすすめ書籍は、下記です。
Essential 細胞生物学
分厚いですが、かなりわかりやすく説明されているので高校生物の知識があれば理解することができます。
解剖学と生理学
解剖学は体の部位・名称を理解するための学問です。一方で、生理学はそれらの機能の基本的なしくみを扱います。
解剖学は生理学と連携性が高いため、コメディカル向けの書籍では「解剖生理学」という一体化された書籍も多く出版されています。
しかし、データベース研究において解剖学の知識が必要になることはほとんどないと思います。
そのため、個別に必要性が生じた際に勉強することにすればよいと思います。
どうしても取り組みたい方は、下記の本がおすすめです。
難しい読み方の専門用語にフリガナがふられており、学びやすいです。
・ぜんぶわかる人体解剖図―系統別・部位別にわかりやすくビジュアル解説
生理学は、人体を構成する組織や器官、そのしくみについて学ぶ学問です。
例えば、脳にどのような神経があり、それにつながっている脊髄にはどのような神経があって、
それが体の臓器にどのような命令を下しているか等です。
とにかく、人間の体について学びます。
細胞生物学と似ていますが、生理学の方がよりマクロな視点で語られます。
生化学
生化学は、生物と化学の融合というイメージがあるかもしれません。
実は、それらとは別の学問です。
生化学は細胞生物学と似ており、オーバーラッピングする部分もあります。
細胞生物学よりもよりミクロな視点で化学反応を学びます。
例えば、細胞の中のミトコンドリアで起きている化学反応や体を構成しているアミノ酸やその合成方法等。
体の中に入ってくる分子(例えばビタミン)にはどのような機能があり、それはどのような反応に役立つのか。
意外と思われるかもしれませんが、生化学的な異常は疾患につながるため(特に代謝や血液)、人体に対する深い理解が得られます。
また身近な知識として、検体検査で実施される血液検査、尿検査で測定される分子の形態なども分子レベルで機能が学べ、理解を深めることができます。
免疫学
型コロナウイルスの蔓延により、免疫学はさらに注目されています。
新型コロナのワクチンを打つ打たないの判断、mRNAワクチンとは何か?
免疫学を学べば、このあたりの回答は自然と得られます。
おすすめの書籍は下記です。
・シンプル免疫学
レベルは比較的高く、医師国家試験の一歩手前程度の詳しさで解説されています。
免疫学の場合、簡潔に書かれた書籍は理解しにくい性質があるのでどうしてもこのレベルの参考書がおすすめになってしまいます。
最先端の知識や常識
おさえておきたい分野として、「ゲノム編集」が挙げられます。
なんとなく、「遺伝子に関する知識?」と思う方もいるかもしれませんが、それとは少し別物です。
私は、このあたりの基本的な知識を補完するために、「日経サイエンス」愛読していました。
教科書には掲載されていない最新の医学常識を得ることができます。
ただし、日経サイエンスは基本的な生物学の知識がないと理解することが難しいと思います。
お手軽な表紙をしていますが、結構専門性が高いのです。
以上が私が行った基礎医学系知識に関する取り組みです。
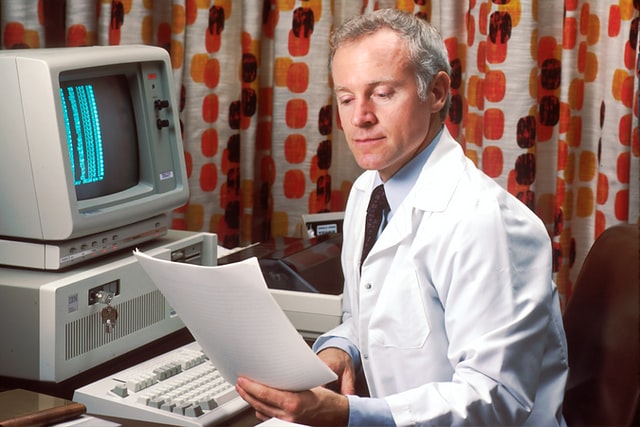


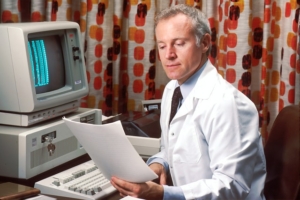
コメント