医療統計学は、別名生物統計学とも呼ばれますが主に臨床研究で頻用される統計学です。
普通の統計学とは少し違って、開発した医薬品や医療機器の効果を立証するために使われます。
また、疫学研究においても同様の手法が使われます。
私は、統計の専門家ではありません。
専門というのは奥が深く、一定の研鑽を積まなければなりません。
例えば、医療系データが与えられたとき、統計の専門家は解析に用いる手法に迷いがありません。
しかし、我々のような素人は、どの統計手法を用いようか、あるいは用いれば良いのか、判断がつかない場合があります。
どの手法を用いるかというのは、医療統計の中で「研究」ではなく、「業務」に該当します。
素人は、どの学術分野でもそうですが、「研究」はおろか「業務」の水準にすら達しないことが多いです。
目次
基本の統計学を習得する
はじめに、一般的な統計学の知識を得ることから始めます。
入門書は色々見ましたが、下記の本が最も良いと感じました。
かなり分かりやすく説明されていることに加えて、他の入門書にはあまりのっていない標準正規分布やカイ二乗分布の成り立ちから説明されており、理解が深まります。
リンク
医療統計学の習得
医療統計学に関しては参考書がたくさん出ていますが、基本的なことは下記の2冊をお勧めします。
回帰分析や一般的な検定が詳しく説明されており、特に医療統計で頻用される分割表に関しては複数章が割かれています。
ただし、ひとつ欠点を挙げると、医療統計で頻用される生存時間解析等が載っていない点です。
生存時間解析を使う方は、他の書籍で補う必要があります。
リンク
リンク
各論の習得(生存時間解析、ベイズ統計・・)
これまで紹介した書籍は、各論まで深くは踏み込んでいません。
しかし、生存時間解析や分散分析等身に着けておいたほうが良いものがあります。
それらについて分かりやすく取り上げている本を紹介しておきます。
リンク
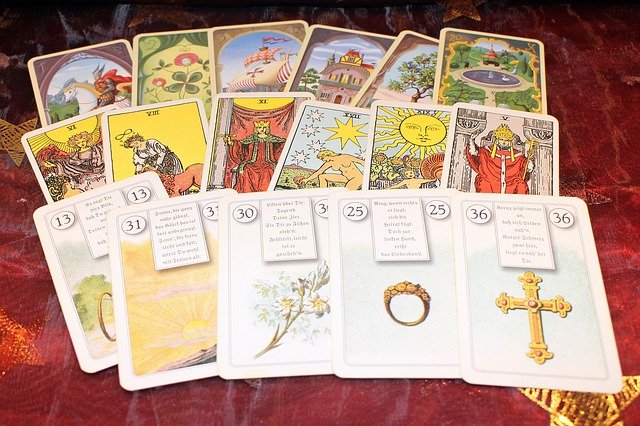


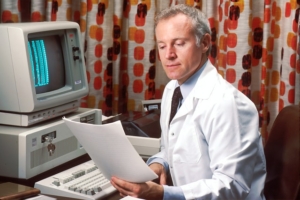
コメント